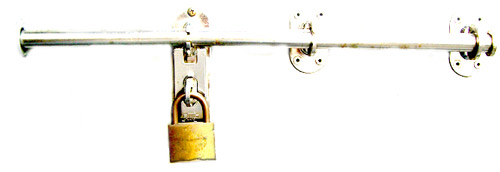|
|
|
鳴く声 |
|
既に夕闇は豪雨と共に深くなり、屋敷の奥に位置する台所の地下がいかほどの広さなのかを目で確認することはできなかった。 優人は手近にあった小石をその中に投げ入れ、その反響音に首を傾げた。 石は僅かな時間を置いて直ぐに地面にぶつかり、そこからコロコロと奥に向かって転がっていった。その様子に優人は首を傾げ、山崎に問いかけた。 「部屋みたいだな。日本家屋にも地下室ってあるの?」 優人の問いかけに山崎はぷるぷると首を振った。 「普通はないよ」 「そうだよなぁ。じゃぁこれは、ブルジョアの食料庫だったと考えればいいのかな?」 「あ!」 その時山崎は大声を張り上げ、そのまま反射的に後ずさった。 「何?」 優人が面倒そうに問いかけると、山崎はびくびくと後ろを振り返りながら、小さな声で付け足した。 「あのさ・・・・ここって戦時中にはあったらしいんだ」 「戦時中?」 「第二次世界大戦」 優人は耳慣れない単語にしばし頭をひねったが、直ぐに意を解して頷いた。 「てことはだよ、これって防空壕なんじゃない?」 「ぼーくーご―?」 明らかに意味を知らない人間の平坦な発音に、山崎はイライラと頭を掻いた。 「ああ、お前知らないか!あのな、山とか家の庭とかに穴掘って、空襲があった時にそこに逃げ込むようにしてたんだよ。今で言うと手作りの民間用シェルター」 「これが?」 「生で見たことないからはっきりとは言えないけど、多分こんなんじゃないかな」 山崎はそこまで言うとぶるぶると首を振った。 「でもよくそこで人が焼け死んだりしたんだって読んだことある。単なる穴だから、火に囲まれると逃げ道なくて、そのまま焼け死ぬんだって。だからこの声もきっとそうやって死んだ赤ん坊とかなんだよ!」 今にも失神しそうな山崎に、優人は僅かに頷き、それから首を横に振った。
「違うんじゃない?」 「はぁ?!」
噛み付きそうな勢いで詰め寄る山崎に優人はいなすように微笑み、肩を叩いた。 「幽霊だったら、僕がこれだけ側にいるのに変わらず泣いていることなんてできないはずだ。とっくにどこかに飛ばされている。だからこれはきっと別の原因があって聞こえる声らしきもののはずだ」 「何?お前何言ってんの?!意味分かんねぇ!!」 目を白黒させる山崎に、優人はため息をつきつつ真正面を向いた。 「お前たちがさっき言っていたじゃないか」 「何?」 「僕の弟には霊感があるって」 怪訝そうな表情をした山崎を宥めるように優人はことさらゆっくりと話しかけた。 「その弟の言うことには、僕は幽霊を撥ね付ける特性があるらしい。効果は自分の周囲だけらしいけどな。幽霊、悪霊、呼び名はどうでもいい。何でもかんでも弾き飛ばす。だから本物の幽霊がいるなら、僕の周囲からは一時的にせよ姿を消すし、万が一僕より強い幽霊がいたとしても、その場合はなんとしても僕はその場に近づけないんだ」 「!?」 「そこがスポットだっと知らなくとも、絶対に僕はそこに近付けない。具合が悪くなったり、自転車が壊れたり、犬に噛まれたりして辿りつけないようになっている」 優人はそう言うと、切れ長の瞳を僅かに細めた。 「だから僕がこうしてここにいるのに声がするってことは、この原因は幽霊じゃないってことになる」 突然の優人の説明に山崎はぽかんと大口を開けたが、直ぐに縋るように優人の腕を掴んだ。 「そんな・・・・・・嘘だろ?」 「嘘をついてどうする」 「でも、弟が言っていることだろ。そんなん信じられるかよ!」 「弟だけど、晴人はちゃんと専門家たちに認められた霊能力者だ」 「専門家?」 山崎が繰り返した単語に、優人は少し話し過ぎたと顔を顰めたが、弁明するのも面倒だと、そのまま正直に事実を語った。 「弟は日本有数の霊媒師に中国の道師、それから・・・・心霊現象の研究家に認められている霊能者なんだ。テレビで放送されるようなものよりよっぽど信用できる認定だよ。実際、今までの経験で言えば、晴人の霊視結果は100%事実だった」 「・・・・・」 「そして弟が言うように、今現在まで僕は自分の目で幽霊を見たことはない」 見たいと願ってもね。 と、優人が付け加えると、山崎は不思議そうな顔をした。 優人は苦笑し、それで話は終わったとばかりにその場に屈み込んで扉の中を覗いた。 「懐中電灯があればいいんだけど・・・・暗くてよく見えないな。あ、なんだ梯子がある。ちょっと降りてみてくるから、ここで待ってろよ」 「谷山?!」 そうして優人が身を乗り出し、山崎がそれを止めようとした瞬間。 ビカリと、爆撃さながらの光が部屋に差し込み、直後に大音響で雷鳴が鳴り響いた。 「うわぁぁあああ!!!」 「あ!」 驚いて体勢を崩した山崎はそのまま身を乗り出して地下を覗いていた優人にぶつかった。 虚をつかれた優人が2人分の体重支えきれるはずもなく、そのまま2人はもろともに地下の空間に落下した。
どのくらいしたのか、耳元で聞こえるその泣き声に山崎は目を覚ました。 気を失ってしまったのだろう。 そう思考が追いついた瞬間、さっきより随分側で聞こえる声に山崎はさっと顔色を変えた。
「 なぁぁぁあん・・・・・なぁ・・・・ああああぁあぁん 」
やばい。 やばい。 やば過ぎる。
さぁっと血の気が引き、背中に冷たい汗が流れた。 肌がざわりと粟立つほど、すぐ耳元でその声は響いた。 山崎は慌てて体を起こした。 が、そうして付いた手元は、ふにゃりと生温かい感触があった。
「うっっ・・・・・・わぁぁぁぁあああああ!」 「うるさい!!」
溜まらず悲鳴を上げた山崎に対して、間髪入れずに怒鳴り声がそれを制した。 その声の主に山崎は泣き出さんばかりに飛びついた。 「谷山!」 「耳元で騒ぐなバカ」 「なぁぁ・・・・ん」 「ぎゃぁぁぁぁぁああ!」 「やかましい!!!!」 「だって!!!」 「あ・・・・・ふぅぅにゃ・・・・・あぁぁぁん」 「うわぁぁぁぁ!!!」
「猫だ」
「きゃぁぁ・・・・・・あ・・・・・あって、は?!」 涙すら浮かべて慌てふためいていた山崎はその単調な声にぴたりと動きを止めた。 「猫・・・・ Cat . Do you understand ?」 周囲は一寸先も見えない闇でまるで地獄にいるようだった。その闇の中からにゅっと白い手が伸ばされ、山崎の前に痩せた猫が一匹押し付けられた。 「うわぁ!」 「何だよ。猫まで怖いのか?」 「ねねね・・・・・ねっこぉぉ?」 あぁぁ、と鳴く猫を抱きかかえながら、山崎はへたへたと脱力した。 先ほどまで聞こえた声は、確かに目の前に差し出された貧相な猫から発せられた鳴き声だった。 「な・・・・なんだよ。猫?この声・・・・赤ちゃんじゃなくて、猫?」 「事実なんてそんなものだ」 暗闇によく響く声がため息とも付かない息を吐きながら、優人は呟いた。 「お前が倒れてくるから一緒に落ちちゃったじゃないか」 優人に指摘され、山崎はあわてて上を見上げた。 すると薄っすらと四角に切り抜かれた穴が見え、そこから頼りないほど僅かな光が差し込んでいるのが見えた。山崎は慌てて猫を脇によけて立ち上がり、その穴に手を伸ばした。しかし今少しという所で届かない。次いで山崎は直ぐ側にあった梯子に手をかけ登ろうと試みたが、木でできたそれは屋敷同様に腐敗し、手をかけた端からぐずぐずと崩れた。 「何だよこれ?!」 山崎は地団太踏み、何か足をかけるものはないかと闇の中を手探りで探った。 しかし落ちていたのは足をかければ底が抜けそうな木箱や、何の足しにもならないような畳、割れた花瓶と捨てられた空き缶があるばかりでめぼしいものは何一つなかった。 いよいよ追い詰められて山崎は四角い穴に向かって大声を張り上げた。
「ちょっ・・・・誰か!誰か助けて!!!おぉい!野村ぁ!川田!!おおおぉい!!!」
しかし、いくら声を張り上げても聞こえてくるのは少し遠くなった雨音と雷鳴ばかりで、救援を求める声に返事はなかった。 絶望的な気持ちで山崎が上を仰いでいるとそこに先ほどまで恐怖の象徴だった声が細く響いた。 「なぁぁぁん」 暢気な猫の鳴き声に、山崎はカッとなって声のした方を振り向いた。 僅かに差し込む雷光に照らし出されて、僅かに見えるのは鳴く猫と優雅に地面に腰を押し付けたままそれをあやす優人だった。そのあまりに暢気な様子に山崎は怒声を張り上げた。 「これじゃぁ出れないじゃん!」 「そうだな」 「そう・・・って、何のんきにふんぞり返ってんだよ!?やべぇじゃん!」 「そうだな」 「谷山のせいじゃねぇか、何とかしろよ!?」 理不尽な怒鳴り声に優人はあからさまに眉間に皺を寄せ、くっと顔を上向かせた。 「元はと言えば山崎たちがこんな場所に行こうといったのが原因。すりかえるなよ」 「ここまで深追いしなければよかったんだよ!」 「なら付いて来なければ良かっただろう。もしくはあそこで僕を突き落とさなければ良かったんだ」 優人はしれとそう言うと、懸命に鳴き続ける猫の頭を撫でた。 「お腹空いてるんだな。お前もこんな所に落ちなければ、ここまで飢えなくて良かったのにな」 「谷山!!」 山崎は焦れて乱暴に優人の手を引いた。 猫が驚いて優人の膝から飛び降り、優人は立ち上がろうとしたがそこで低い悲鳴を上げた。 「・・・・っっ!」 「え?」 驚いた山崎が手を離すと、優人はそのままゆるゆると地面に座り込み、不機嫌な声で山崎を嗜めた。
「落ちた時に足首ひねったんだ。どちらにせよ動けない」
優人はそう言うと軽く舌打ちした。
「しくじったな」
思わずそう洩らした優人に、山崎はざっと心臓が冷えるのを感じた。
|
|
|